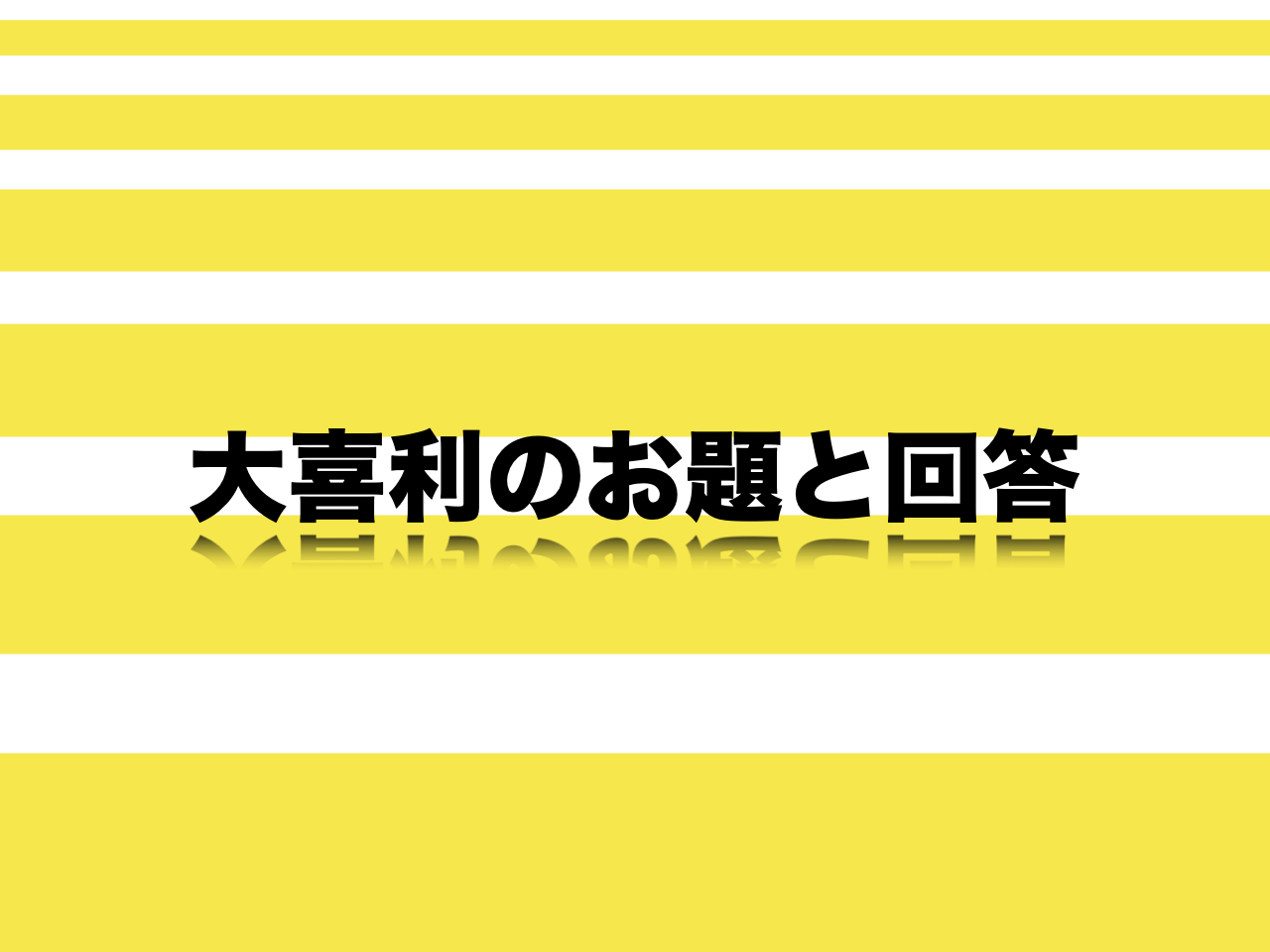はじめに:心理的安全性が大切、と言われても…
「心理的安全性が大切」と言われるようになりましたが、
職場の現場では、相変わらずこんな空気が漂っていませんか?
- 会議で発言が少ない
- 上司の顔色をうかがって沈黙が続く
- 「それ、違うと思う」と言えない
Googleの研究でも、チームの生産性や創造性を高める要素として
「心理的安全性」が最重要とされています。
でも、日本の職場ではそれがなかなか根づきません。
その理由は、「文化的な前提の違い」にあるのではないでしょうか。
1. なぜ日本の職場では会議が黙るのか?
1.1 会議で発言が出ない“あるある”
- 会議が進行するとき、最初の発言者が出るまでに異様な間が空く
- 「何かありますか?」と聞いても「特にありません」が続く
- 空気を乱さないように…という無言の圧力
これ、どの会社でもよく見かける風景ですよね。
1.2 言えない理由は「文化」と「空気」
日本人は「対立」や「異論」を避ける傾向があります。
率直な意見は「空気を壊す」「場の調和を乱す」と受け取られがち。
その結果、会議は“ぬるま湯”のような空気に包まれ、
誰もが本音をしまい込んでしまいます。
2. Googleも重視した「心理的安全性」とは?
2.1 Googleがたどり着いた答え
Googleの生産性調査「プロジェクト・アリストテレス」では、
成果を出すチームに共通する最も重要な要素は「心理的安全性」だと結論づけられました。
2.2 心理的安全性=“率直であれる場”
心理的安全性を提唱したエイミー・エドモンドソン教授も、こう言います:
「心理的安全性とは、安心して発言できる環境のこと。
ただし、それは優しさではなく、率直さが許されることを意味する」
つまり、本音や異論を出しても「非難されない」「疎外されない」と感じられる環境こそが重要なのです。
3. 日本における「心理的安全性」のむずかしさ
3.1 衝突を避ける文化的なクセ
日本社会では「和をもって貴しとなす」という価値観が根強くあります。
そのため、率直さ=失礼・攻撃的と誤解されやすい。
3.2 無言の圧力が“ぬるい空気”を作る
誰かが異論を言おうとする空気を読み、先に黙る。
結果として、**「沈黙は正解」**という合意が無意識に成立します。
これが、日本の職場で心理的安全性が機能しにくい根本の要因です。
4. カギは「笑い」にある!ツッコミ文化の可能性
4.1 日本独自の“笑って本音を言う”土壌
日本には、漫才やコント、ツッコミといった「笑いの文化」が根付いています。
これを活用すれば、笑いながら本音を伝えることが可能になります。
4.2 笑いがあると異論も言いやすくなる
笑いが場にあることで、人は「責められる」不安が和らぎます。
- 冗談交じりに意見が言える
- ユーモアが“場のクッション”になる
- 緊張感がやわらぐことで「言い出せる」空気が生まれる
4.3 笑いが“共通言語”になるとき
特定の笑いのスタイル(たとえばツッコミ)をチームで共有することで、
対話がスムーズに流れるようになります。
5. でも「笑ってごまかす」は逆効果
5.1 ごまかしの笑いは信頼を壊す
笑って本題を避ける「やんわり回避」は、むしろ危険です。
心理的安全性の本質は「率直にぶつかること」にあるからです。
5.2 平時から“笑いの習慣”を育てる
緊張時だけ笑いを使うのではなく、
日常的に笑いがある場づくりをしておくことが、信頼と率直さを両立させるカギです。
6. まとめ:笑いと率直さが共存するチームへ
心理的安全性は、単なる「優しさ」ではなく、衝突を恐れず、戻れる安心感があることです。
心理的安全性は「仲良しグループを作ること」ではありません。
むしろ、「ぶつかることを恐れず、率直に語り合えること」が、本当の意味での安全性を育てます。
しかし、日本の職場では「衝突=悪」とされがち。
その壁を越えるために有効なのが、“笑い”や“ユーモア”という文化の力です。
– 笑いがあれば、異論を出しやすくなる
– ユーモアがあれば、場の緊張をほぐせる
– 共通の笑いがあれば、衝突から“戻れる”余白が生まれる
つまり、笑いは単なるムードづくりではなく、「職場の心理的安全性を支えるエンジン」なのです。
これからの職場には、「笑いながら本音で話せる文化」が欠かせません。
ユーモアがあるからこそ、率直に語り合える。
そして、ぶつかっても温かく戻れる──そんなチームが、成果を生み続けるのです。